2019年6月29日土曜日 埼玉県現代俳句協会で青年部長神野紗希氏講演 小雨が降る埼玉県川口市の川口総合文化センターで行われた埼玉県現代俳句協会大会で神野部長が講演した。 演題は「偶然、他者、肯定の詩」 これは大胆にも山本健吉の「滑稽・挨拶・即興」に対する神野さんの解釈?いや挑戦?であろうか。 「俳句は、偶然を受け入れ、新しい他者との出会いを受け入れる、肯定の力に満ちた詩ではないか」 神野氏によれば、挨拶・即興は偶然を受け入れる姿勢であると考える。その意味で、 写生は偶然を受け入れることの肯定的行為となる。 (実に刺激的な解釈だ by章) 柿食へば鐘が鳴るなり法隆寺 子規 たまたま食べたところに鐘が鳴った偶然であるが、神野氏は、この偶然を俳句に取り込む子規の横紙破りを指摘する。つまり和歌では食べる行為を詠わないのであった。子規はあえてそれを取り込んだ。偶然を肯定したからだと言う。 では他者とは何か? つまり、上記のように和歌の慣習では見過ごされてきたものが新しい他者である。例として下記の句も示された。 木の下に汁も膾も桜かな 芭蕉 あたたかな雨が降るなり枯葎 子規 九鬼周造の『偶然と驚きの哲学』を引用して彼女は言う。 「偶然性とは、AとBとの出会いによって生じる」と。 鶯や餅に糞する縁のさき 芭蕉 雨がふる恋をうちあけやうと思ふ 片山桃史 心中は途中でやめにして銀漢 三根詩生(俳句甲子園) 等の句を示して出会いの偶然性を説明した。 総括として彼女は次のように締めくくった(一部) 「俳句は、過去の詩歌に見過ごされてきたものたちの中に、生きる命の在り様を見つけ、(中略)命を吹き込んできた。偶然訪れた他者を受け入れる積極的な肯定こそ、私たちの価値観をアップデートし、世界を一つ増やしてくれる、俳句の底力。」 また、神野氏は現在一児のママとして、子連れの句会などを積極的に開いて、この世代の俳句をしながら育児をするママを応援している。それには先行として杉田久女や竹下しづの女の次のような句が勇気を与えてくれたという。 仮名かきうみし子にそらまめをむかせけり 杉田久女 短夜や乳ぜり泣く子を須可捨焉乎 竹下しづの女 ...





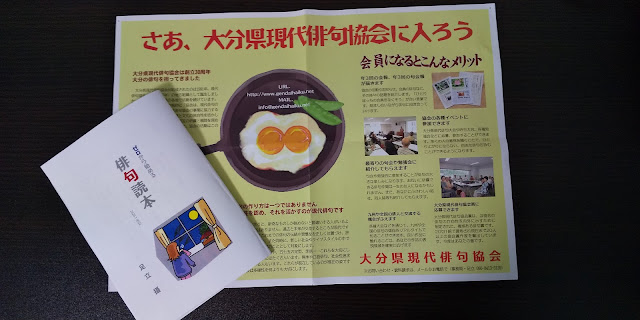
コメント
コメントを投稿